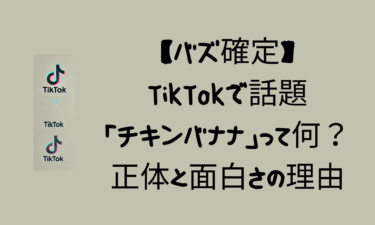2024年4月1日から、口コミ投稿に新たな規制がスタートしました。
「えっ、普通のレビューもダメになるの?」と不安に思った方も多いのではないでしょうか。
実は今回の改正では、報酬や商品提供を受けたレビューに「広告」や「PR」の明示が義務づけられるなど、私たちがよく使うSNSやブログ、ECサイトの投稿にも直接影響があります。
この記事では、具体的にどんな内容が規制されるのか、過去の炎上事例や企業の対応例も交えながら、わかりやすく解説していきます。
「これはセーフ?アウト?」と迷った時の判断ポイントも紹介しているので、ぜひ最後まで読んで参考にしてくださいね。
2024年4月1日から口コミ投稿に制限がかかる理由
2024年4月1日から口コミ投稿に制限がかかる理由について解説します。
それでは、それぞれの項目を詳しく見ていきましょう!
①改正景品表示法による規制強化
2024年4月1日から、景品表示法が改正され、口コミやレビューといったユーザー投稿にも厳しいルールが適用されるようになりました。
今までは主に「企業が出す広告」に対する規制が中心でしたが、今回の改正では、**第三者である一般ユーザーの投稿でも、企業から報酬や提供がある場合は広告として規制対象になる**ことが明文化されました。
たとえば、インフルエンサーが企業から商品をもらって投稿したのに、それが広告であることを明記していなければ、景品表示法違反となる可能性があります。
「個人の感想です」みたいな逃げ道は、今後は通用しなくなるんですね。
つまり、口コミも「広告に準じたもの」として、しっかり取り締まりの対象になってきたんですよ。
②ステマ投稿の明示義務が追加された
今回の改正のキモともいえるのが、**ステルスマーケティングの明示義務**です。
企業が金銭・物品・サービスなどを提供して口コミを書かせるなら、「これは広告です」と明記しなければいけません。
これはSNSの投稿やブログ記事、レビューサイト、ECの評価欄など、すべてのプラットフォームに適用されます。
つまり、「この商品マジで最高!自腹で買ったけど、リピ確定~!」みたいな投稿をしていて、実は企業から案件として報酬をもらっていた場合、それを明示していなければNGです。
今後は「PR」「広告」「プロモーション」などの文言を、投稿の冒頭など目立つ場所に記載するのが必須になりました。
③「やらせレビュー」の取り締まりが厳格化
さらに注目されているのが、「やらせレビュー」への規制強化です。
たとえば、まだ商品を使っていないのに、企業から依頼されて良いレビューを書くこと、いわゆるサクラ的な投稿は完全にアウト。
ECサイトでよく見かける「☆5評価が異常に多い新商品」なんかは、これまで黙認されがちでしたが、今後は監視対象になります。
Amazonや楽天などのレビュー欄で、報酬目当てに「実際に体験していない」のに投稿する行為は、消費者を誤認させる不当表示となる可能性が高くなりました。
実際に、そういった投稿を斡旋していた業者が摘発される例も出てきています。
④企業によるレビュー操作も違法に
消費者庁が特に強く警鐘を鳴らしているのが、「企業によるレビュー操作」です。
たとえば、企業がネガティブなレビューだけを削除したり、評価の高いレビューだけを表示させるような仕組みを作っていた場合、それも表示法違反となります。
これは「プラットフォーム側の責任」にも関わる話で、レビュー投稿の自由や透明性が確保されていないと、その場全体が信頼を失ってしまいますよね。
レビュー欄を広告のように操作しようとする企業の姿勢には、今後ますます厳しい目が向けられるでしょう。
いずれにしても、「本当に使った人の率直な声」を大切にする時代にシフトしてきているといえます。
制限される口コミ投稿の具体例4つ
制限される口コミ投稿の具体例4つについて解説します。
実際にどんな投稿がアウトなのか、わかりやすく紹介していきますね。
①報酬を受けたのに「広告」と書かない投稿
まず、もっとも明確にNGとなるのが「広告であることを隠して投稿するケース」です。
たとえば、InstagramやTwitter(X)で「この美容液ほんとに最高!肌つるつる!」と紹介しているのに、実は企業からお金をもらっている…そんな投稿、見たことありますよね。
このように、**報酬や商品提供を受けているのに“あたかも個人の感想”のように見せる**のは、典型的なステマに該当します。
景品表示法の観点からも、「広告」「PR」「タイアップ」などの文言を明示しなければならないとされており、これを怠ると**企業側だけでなく、投稿者本人も罰則対象**になることがあります。
今後は「案件」として書く際には、明記が必須ですよ〜。
②未購入・未体験なのにレビューする行為
実際には使っていないのに「めちゃくちゃ良かった!買って正解!」みたいなレビューを書く行為も、完全にアウトです。
たとえば、企業が報酬と引き換えに高評価レビューを書かせていたり、レビュー投稿代行を請け負うような業者が「サクラ」を集めてレビューを書かせている場合があります。
こういった投稿は、消費者を誤認させる恐れがある「不当表示」とみなされ、特定商取引法や景品表示法に違反するリスクがあります。
実際に、Amazonでこのような“やらせレビュー”を大量に投稿していた業者が摘発された事例もあり、今後はさらに厳しい目でチェックされていくでしょう。
自分で体験していないものは、絶対にレビューしない!これ、鉄則です!
③商品提供を受けた体験談の“さりげない宣伝”
意外と見落としがちなのが、この「ソフトPR」タイプの投稿です。
たとえば、企業から商品を“無料提供”された場合、お金はもらっていないけど、レビューを書いたらプレゼントされた…こんな場合も、広告とみなされます。
「案件じゃないけど、もらったし…せっかくだから投稿しよう」みたいな気持ちで投稿しても、それが**商品提供による影響を受けた内容であれば、ステマに該当**します。
こういったケースでも、「企業からの提供あり」と明示することが求められています。
「提供:〇〇株式会社」など、目立つ場所にしっかり記載しておきたいですね。
④企業がネガティブレビューを削除する行為
最後に紹介するのは、投稿者ではなく「企業側」のNG行為です。
たとえば、自社ECサイトや公式レビュー欄で、★1〜2の低評価レビューだけを削除したり、目立たないように非表示にしたりするような行為は、明確にアウトです。
プラットフォーム運営者がこうした操作をすることで、消費者にとって“実際より良く見える”印象を与えるため、不当表示の対象となります。
特に自社メディアでレビュー機能を設けている企業は、表示ルールに注意する必要があります。
「都合のいいレビューだけ載せる」ってやつ、もう通用しませんよ~。
実際の口コミ体験談から見る注意点5つ
実際の口コミ体験談から見る注意点5つについて紹介します。
リアルにあった事例から、これから気をつけるべき点が見えてきますよ。
①InstagramでPR明記せず炎上したケース
ある女性インフルエンサーが、自身のInstagramでとある美容商品の投稿をしました。
「まじで肌が生まれ変わった…これはもう手放せない!」と、かなり熱の入った紹介をしていたのですが、実はその投稿は企業案件。
にもかかわらず、「#PR」「#広告」といった明記は一切なし。
フォロワーから「案件なのに隠してたの?」「ステマじゃん」と炎上し、コメント欄が大荒れになりました。
結局、後日謝罪し、投稿に「提供を受けた広告である」旨を追記しましたが、失った信頼は簡単には戻りませんでした。
案件であることを明示しないと、読者やファンの信頼も失います。これは一番の学びですね。
②YouTube案件で案件表記漏れの問題
YouTuber界でも似たようなトラブルは発生しています。
とある中堅YouTuberが、動画内であるガジェットを大絶賛。
「これ、本当にすごい。自分で買って試して正解だったわ」と紹介していましたが、実際は企業からの案件でした。
動画の概要欄にも案件表記はなく、視聴者からの指摘で発覚。
消費者庁に報告が入るレベルにまでなり、後日、当該YouTuberは釈明動画を投稿することになりました。
YouTubeも広告と認識される範囲が広いため、「提供:〇〇」「プロモーションを含みます」などの表記は必須です。
視聴者の信頼を守るためにも、必ず事前に表記しましょう。
③Amazonで報酬付きレビューの摘発事例
Amazonでは、過去に「報酬付きレビュー」の取り締まりが強化されています。
特に2022年ごろから、商品を提供しつつ、高評価レビューを書いてもらう代わりにギフト券や謝礼を渡す…といった手法が横行。
これに対してAmazonが大規模な調査を実施し、**数百件以上のアカウントを削除・レビューを削除する対応**を取りました。
レビューの信頼性が問われる中で、「本当に使った人の声」が重要視されており、やらせ投稿は即アウトです。
ECでの信頼は、ルールを守ったレビュー投稿が支えています。
④ブログで“レビュー風広告”と指摘された件
とあるアフィリエイト系ブログでは、「おすすめランキング」として商品を紹介する記事が掲載されていました。
記事のタイトルは「個人の感想」としての体裁を取りつつ、実際には全商品が提携している広告リンクでした。
消費者庁により、**「ランキング形式での広告表示は、明確な表記がなければ誤認を招く」**との判断がされ、注意喚起がなされました。
こういった「レビュー風に見せた広告記事」は、今後も厳しく取り締まられる可能性があります。
読者に誤解を与えないよう、「この記事はアフィリエイトリンクを含みます」などの表記は必須ですよ!
⑤企業側が評価操作して行政指導を受けた話
最後は企業側のケースです。
某美容メーカーが自社ECサイト上で、「★3以下のレビューを非表示設定にしていた」ことが判明。
消費者庁が調査を行った結果、「表示の仕方に問題がある」として行政指導が入りました。
また、社内で良いレビューを社外ライターに書かせていたことも発覚し、信頼を大きく損ねる結果に。
今後はレビュー表示の透明性が求められる時代です。
企業側も、ユーザーの声をそのまま受け止め、真摯に向き合う姿勢が必要ですね。
これからの投稿で気をつけるポイント5選
これからの投稿で気をつけるポイント5選を紹介します。
ここでは、「違反しないために」「信頼を得るために」必要なことを整理しておきましょう。
①「広告」や「PR」をしっかり明記する
まずはこれ、**絶対中の絶対に必要なこと**です。
企業案件だったり、商品提供を受けて投稿する場合には、「これは広告です」「PR投稿です」と、はっきり書きましょう。
Instagramなら冒頭に「#PR」「#提供」といったタグ、YouTubeなら動画タイトルか概要欄に「プロモーションを含みます」と記載するのが安心です。
ブログや口コミ投稿の場合も、「この記事は企業から商品の提供を受けて作成しました」と記載することで、読者に誤解を与える心配がありません。
信頼って、透明性の積み重ねですからね。ここをサボらずいきましょう!
②本当に使った商品だけを紹介する
「ちゃんと使ってるかどうか」って、意外と読者やフォロワーにバレてます。
使ってないのに「めっちゃ良かった!」なんて書くと、薄っぺらさがにじみ出ちゃうんですよね。
これからの時代は、誠実なレビューが求められます。
だからこそ、「本当に使った」「試してみた」商品だけを紹介するのが基本中の基本です。
その過程で感じたメリットもデメリットも、リアルに語ることで、信頼性の高い口コミになりますよ。
③正直な感想を書く
良いことだけ書くと「なんか怪しい」って思われがち。
だから、「良かった点」「ちょっと気になった点」も含めて、正直に伝えることが大事です。
たとえば、「保湿力は高いけど、香りは少し強め」とか、「コンパクトで便利だけど、バッテリーは1日しか持たない」など。
こういうリアルな声って、読んでる側にとって一番ありがたいんですよね。
「ウソなし」「盛らない」「ゴマかさない」この姿勢が、信頼を勝ち取る近道です。
④レビューは操作しない・させない
企業側としても、レビュー欄の“操作”には注意が必要です。
低評価を削除したり、投稿前に内容を確認して修正させたり…こういった行為は、消費者に対する誤認表示になりかねません。
投稿者としても、「修正して」「この表現はやめて」と言われたときは、一度立ち止まって考えてみてください。
「これ、本当に消費者のためになってる?」と。
本音のレビューを届けるためには、企業も投稿者も、お互いに誠実な姿勢が必要なんですよね。
⑤案件であっても信頼される発信をする
「案件だからって信頼されない」時代は終わりつつあります。
むしろ、きちんと「これは案件です」と明示して、**そのうえで本当に良かった部分・イマイチだった部分を素直に伝えてくれる人**が、逆に信用されるようになっています。
最近は「PRでも信頼できる人」をフォローする人が増えていますし、フォロワーの見る目もどんどん鋭くなっています。
案件であっても、自分の言葉で、真っすぐに発信する。それが結局、長い目で見て一番得になるんですよね。
堂々と「これはPRです!」って言える自分、カッコよくないですか?
口コミ規制は悪なのか?今後の展望と向き合い方
口コミ規制は悪なのか?今後の展望と向き合い方について解説します。
「規制」って聞くとちょっとネガティブに感じるかもしれませんが、実はけっこう前向きな意味もあるんですよ。
①消費者が守られる環境づくり
まず一番大事なのは、やっぱり「消費者が安心して商品を選べる環境」を作ることです。
口コミやレビューって、ほとんどの人が買い物の判断材料にしてますよね。
そこにウソや操作があったら、誰だって損しちゃう。
だから今回のような規制が入ることで、「本当に参考になる声」だけが残る仕組みになっていくのは、消費者にとってめちゃくちゃありがたいことなんです。
誰もが正しい情報で安心して買い物ができる世界って、素敵じゃないですか?
②インフルエンサーの信頼性アップ
規制は、インフルエンサーにとっても悪い話じゃないんです。
むしろ、「ちゃんと明記している人」と「していない人」の信頼格差が明確になってきます。
きちんとPR表記して、リアルなレビューをしている人のほうが、「この人の情報は信頼できる」と評価されていきます。
今後は、フォロワー数よりも「誠実さ」や「一貫性」が重視される時代です。
規制が入ることで、本当に価値あるインフルエンサーが見極められるようになるんですよね。
③透明性のあるレビュー文化へ
これまでの口コミ文化って、「ステマ」や「サクラ」でちょっとグレーな印象があったかもしれません。
でも、今回のルール改正で、レビューや体験談の透明性がぐっと高まっていきます。
実際に、SNSでも「ちゃんとPRって書いてくれる人のほうが安心する」って声も増えてきてますし、ユーザーの目も厳しくなってきています。
これはつまり、投稿者・発信者・企業・プラットフォーム、みんなで「信頼される情報空間」を作っていく時代の始まりとも言えます。
ウソのないレビューが当たり前になる社会、いいと思いませんか?
④企業のモラル向上が求められる
最後に、企業側のスタンスも問われています。
「いいレビューだけ載せよう」「ちょっと言葉を直してもらおう」そんな小さなズルが、今では法に触れることになります。
だからこそ、これからは**誠実なマーケティング**が企業の信頼を左右する時代です。
そして、そんな企業が選ばれるようになります。
企業も発信者も、消費者も、みんなが納得できる関係をつくっていけたら最高ですよね。
これからの口コミ社会は、もっと健全に、もっと信頼できる方向に進んでいきそうです。
まとめ|口コミ投稿に必要な新ルールを正しく理解しよう
2024年4月から施行された景品表示法の改正により、口コミやレビュー投稿に対する規制が強化されました。
特にステルスマーケティングと見なされる投稿や、実際に体験していない商品への高評価レビューなどは、法的な問題に発展する可能性があります。
これからは「広告明示」「本音のレビュー」「透明な情報発信」が当たり前になっていきます。
投稿者自身の信頼を守るためにも、ルールを正しく理解して、安心できる発信を心がけたいですね。
制度の詳細や今後の動向については、消費者庁|景品表示法に関するガイドラインも参考にしてみてください。